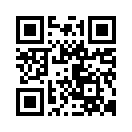› 個人プロボノQ&A ~おしえて、こたえて、助け合い。~ › Q12.収益事業は、どんな事業を、いくらまでしてもいいのでしょうか?
› 個人プロボノQ&A ~おしえて、こたえて、助け合い。~ › Q12.収益事業は、どんな事業を、いくらまでしてもいいのでしょうか?2014年02月06日
Q12.収益事業は、どんな事業を、いくらまでしてもいいのでしょうか?
あなたのお悩み、プロボノで解決!【個人プロボノQ&A】
【Q】収益事業は、どんな事業を、いくらまでしてもいいのでしょうか?
(A1)
簡単には、
http://www.fastway.jp/what/10.php
詳しくは
http://blog.canpan.info/waki/archive/160
脇坂さんのHPについては、法改正前の解説のため、17分野の活動となっていますが
基本的には、この解説がベストと思います。。
(A2)
「収益事業」といった場合、2つのことを指していると考えられます。
(1)旧NPO法における、「特定非営利活動」に対する「収益事業」。現在の「その他の事業」。
(2)法人税法における、法人税の申告対象となる「収益事業」。
それぞれの取り扱いについては、下記の通りとなります。
(1)旧NPO法における「収益事業」(現在の、「その他の事業」)
「その他の事業」はあくまでも「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされています(NPO法5条1項)。具体的に実施できる事業内容ですとか、金額の上限などについては規定がありません。
その他の注意事項については、下記の記事が参考となります。
http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=79
(2)法人税法における「収益事業」
こちらもどんな事業をいくらまで実施してよいのかという規程はありません。
実施している事業のうち、法人税法に規定する「収益事業」については区分して経理をし、法人税の申告・納付をしなくてはなりません。
(○円以下であれば申告不要、という規定もありません)。
(1)法人税等
①納税義務
NPO法人が実施する事業であっても、法人税上の「収益事業」に該当すれば、所得に対して法人税が課税されます。
NPO法上の「その他の事業」が、法人税法上の「収益事業」であるわけではありません。つまり、NPO法上は「本来事業」であっても、法人税法上「収益事業」に該当することがあるのです。
(例)
法人税\NPO法
特定非営利活動に係る事業
(本来事業)
その他の事業
収益事業
法人税法の対象となる事業
非収益事業
法人税法上、収益事業は「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの」と規定されています(法人税法第2条第1項13号)。
★販売業・製造業その他政令で定める事業とは
下記34業種に当てはまる事業は、NPO法上の「本来事業」であっても法人税法上は「収益事業」に該当します。
1)物品販売業 2)不動産販売業 3)金銭貸付業 4)物品貸付業 5)不動産貸付業
6)製造業 7)通信業 8)運送業 9)倉庫業 10)請負業
11)印刷業 12)出版業 13)写真業 14)席貸業 15)旅館業
16)料理店業その他の飲食店業 17)周旋業 18)代理業 19)仲立業
20)問屋業 21)鉱業 22)土石採取業 23)浴場業 24)理容業
25)美容業 26)興行業 27)遊技所業 28)遊覧所業 29)医療保健業
30)技芸教授業 31)駐車場業 32)信用保証業 33)無体財産提供業 34)派遣業
★継続性
収益事業は「継続して事業場を設けて営まれるもの」と定義されていますので、例えば「1年に1回のバザー」などは「物品販売業」に該当していても、「継続性がない」と判断されれば「非収益事業」となります。
★非課税規定
法人税法については、さまざまな非課税規定があります。 例えば、上記34業種の事業に従事する障害者等がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの[1]については法人税は課されません。
[1] 法人税法施行令第5条第2項第2号(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html)
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
一 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
二 母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年政令第二百二十四号)第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第十四条 (母子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十二条第三項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項 (売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
Probono Saga Style / プロボノSAGAスタイルのホームページへ戻る
>> http://sagaasc.wix.com/probonosaga#!23/c15y7
【Q】収益事業は、どんな事業を、いくらまでしてもいいのでしょうか?
(A1)
簡単には、
http://www.fastway.jp/what/10.php
詳しくは
http://blog.canpan.info/waki/archive/160
脇坂さんのHPについては、法改正前の解説のため、17分野の活動となっていますが
基本的には、この解説がベストと思います。。
(A2)
「収益事業」といった場合、2つのことを指していると考えられます。
(1)旧NPO法における、「特定非営利活動」に対する「収益事業」。現在の「その他の事業」。
(2)法人税法における、法人税の申告対象となる「収益事業」。
それぞれの取り扱いについては、下記の通りとなります。
(1)旧NPO法における「収益事業」(現在の、「その他の事業」)
「その他の事業」はあくまでも「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされています(NPO法5条1項)。具体的に実施できる事業内容ですとか、金額の上限などについては規定がありません。
その他の注意事項については、下記の記事が参考となります。
http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=79
(2)法人税法における「収益事業」
こちらもどんな事業をいくらまで実施してよいのかという規程はありません。
実施している事業のうち、法人税法に規定する「収益事業」については区分して経理をし、法人税の申告・納付をしなくてはなりません。
(○円以下であれば申告不要、という規定もありません)。
(1)法人税等
①納税義務
NPO法人が実施する事業であっても、法人税上の「収益事業」に該当すれば、所得に対して法人税が課税されます。
NPO法上の「その他の事業」が、法人税法上の「収益事業」であるわけではありません。つまり、NPO法上は「本来事業」であっても、法人税法上「収益事業」に該当することがあるのです。
(例)
法人税\NPO法
特定非営利活動に係る事業
(本来事業)
その他の事業
収益事業
法人税法の対象となる事業
非収益事業
法人税法上、収益事業は「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの」と規定されています(法人税法第2条第1項13号)。
★販売業・製造業その他政令で定める事業とは
下記34業種に当てはまる事業は、NPO法上の「本来事業」であっても法人税法上は「収益事業」に該当します。
1)物品販売業 2)不動産販売業 3)金銭貸付業 4)物品貸付業 5)不動産貸付業
6)製造業 7)通信業 8)運送業 9)倉庫業 10)請負業
11)印刷業 12)出版業 13)写真業 14)席貸業 15)旅館業
16)料理店業その他の飲食店業 17)周旋業 18)代理業 19)仲立業
20)問屋業 21)鉱業 22)土石採取業 23)浴場業 24)理容業
25)美容業 26)興行業 27)遊技所業 28)遊覧所業 29)医療保健業
30)技芸教授業 31)駐車場業 32)信用保証業 33)無体財産提供業 34)派遣業
★継続性
収益事業は「継続して事業場を設けて営まれるもの」と定義されていますので、例えば「1年に1回のバザー」などは「物品販売業」に該当していても、「継続性がない」と判断されれば「非収益事業」となります。
★非課税規定
法人税法については、さまざまな非課税規定があります。 例えば、上記34業種の事業に従事する障害者等がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの[1]については法人税は課されません。
[1] 法人税法施行令第5条第2項第2号(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html)
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
一 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
二 母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年政令第二百二十四号)第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第十四条 (母子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十二条第三項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項 (売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
Probono Saga Style / プロボノSAGAスタイルのホームページへ戻る
>> http://sagaasc.wix.com/probonosaga#!23/c15y7
Posted by probono SAGA style at 18:27│Comments(0)